バッテリーが新品同様の状態の場合、下記の時間でバッテリー上がりになってしまうようです。劣化しているとさらに短い時間でバッテリーが上がってしまいます。
バッテリー上がりまでの目安時間
ハザードランプ:5~10時間
室内灯:12時間
ACCモード(アクセサリーモード):4~5時間
ACCモードでテレビやオーディオの長時間利用:30分~
EVやハイブリッドカーもバッテリーが上がります
EVやハイブリッドカーは、大きなバッテリーが搭載されています。そして、バッテリー残量がモニターに出ているので、安心です・・・というのは大きな間違いです。
EVやハイブリッドカーのバッテリーは、2種類搭載されています。
・メインのバッテリーは、「駆動用バッテリー」というような呼び方がされます。モーターへの電力供給用
・もう一つのバッテリーは、「補機バッテリー」と呼ばれます。
モニターに出ているバッテリー残量は、駆動用バッテリーで、ガソリン残量と同等と思ってください。
では、補機バッテリーとは何か。ガソリン車でいう普通の12vのバッテリーです。
(補機)バッテリーは、何に電気を供給するかというと
- エンジンの始動
- アクセサリー(ナビ、ラジオ)
- 室内灯
- ドアキー、窓の電動開閉
- インジケーター
- コンピューター
- 等、駆動用以外への全ての電力供給を行っています。
これらは、ガソリン車、EV、問わず、仕組みは一緒です。
EV車では、停車時にテレビや音楽を聴きながら、バッテリーが上がると言うことが多いです。なぜかというと、ガソリン車と違いエンジン音がしないので、エンジンがかかっているかどうかの判断が付きにくい。つまり、ACCの状態で休憩を取ってしまうミスをするようです。
EV車、ガソリン車も、駆動状態で補記バッテリーに充電を行います。
EV車は、駆動用バッテリー(数百V)からDC-DC変換、12Vへ変換して補記バッテリーに充電。
ガソリン車はエンジンの回転をベルトを介してオルタネーターを回し、発電を行い、バッテリーを充電します。
ガソリン車とEV車のバッテリーはどんなのか

容量の大きさはありますが、基本的に同じです。12~14V。基本的には鉛電池です。リチウムイオンバッテリーのタイプもありますが、常に満充電、ちょい足し充電、常に充電をするため、特性上、鉛電池の方が向いています。

リチウムイオンバッテリーに転換する動きもあります。
鉛バッテリーは結構頑丈。常に電気を流して充電しても平気。
リチウムイオンバッテリーの場合は、充電制御をしっかりしないと行けない。スマホの充電と同じ。寿命を延ばすなら80%程度の充電にとどめる制御をするかもしれない。電池が劣化が進んだら、使う容量を抑えないとダメ。など、過充電しないような制御をすると思います。
リチウムイオンバッテリーは、過充電、過放電が良くない。
鉛バッテリーも過放電はよくありません。しばらく車を使わない場合は、バッテリーの線を外したりすることもあります。バイクは冬の間、バッテリーのターミナルを外すとよく聞きます。外し忘れて春に乗ろうとすると、バッテリーが死んでいて、充電も出来ない事が多いです。
ただ、車の場合、バッテリーを外すと、時計が狂う。ナビが初期化される。窓のオートストップが狂うなど、弊害が多いので、注意が必要です。
ドライブレコーダーの常時通電タイプ。エンジンスターターが付いていると、常にバッテリーから電力供給をしているため、未使用の期間が長いとバッテリーが上がりやすいです。

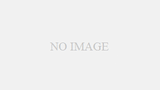
コメント